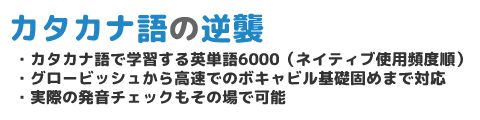column3
母国語でも知らない言葉
新聞を一面から最終面まで熟読する人は少ないでしょう。ほとんどの人は興味があるところだけを拾い読みしているはずです。そして、読み飛ばしている紙面には、日本語ネイティブすら知らない単語が使われていることが珍しくありません。
例えばあなたは、ラグビーの用語をどれほど知っているでしょう? あるいは、医療保険改革の記事をスラスラと読むことができるでしょうか? もしくは、日銀短観の解説記事に使われている経済用語をすべて正確に説明できるでしょうか?
そう、新聞のように万人向けに作られた商品ですら、私たちはそこで使われている言葉に精通しているわけではないのです。これが資格試験のテキストや特定分野の用語集になれば、さらにお手上げになるはずです。いよいよ知らない単語のオンパレードに見舞われるだろうからです。
このように、ネイティブすら知らない単語が身の回りには数多くあるにもかかわらず、私たちは日本語ネイティブとして特に不便することなく生活できています。この辺はうまいこと脳がフィルタリングしてくれているのでしょう。
しかしこれが外国語となると、途端にパニックになります。どこからが特殊な用語で、どこからが普通の言葉なのか判断できず、知らない単語の数の多さに圧倒されがちです。興味の範囲を絞りきれていない場合はさらに深刻で、絶望的な気分に陥ることすらあるでしょう。「こんなにも知らない言葉だらけとは……」と。
けれど、ここはうまく開き直ることが必要です。まず興味の範囲を絞りこみ、そこでの用語に慣れてしまうことです。すると段々と特殊な用語やフレーズの見分けがつくようになります。余裕が出てきたら、徐々に別のジャンルへと手を伸ばしていけばよいでしょう。何も不安がることはありません。ネイティブだって、すべてのことがらに精通しているわけではないのです。ましてや外国語を学んでいる者にとっては、という話です。