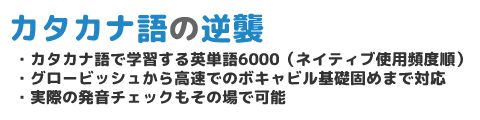高効率で最高速のボキャビル
※これはガチで使える単語力を高速で効率よく身につけたい人向けのコースです。グロービッシュで十分な場合には不要です。
【 高効率最高速ボキャビルの三つのステップ 】
- 当サイトで6000の英単語を身につけます
- JACET8000か、究極の英単語9000までの単語を覚えます
- 自身が興味ある分野、あるいは関与する分野での頻出語を重点的に覚えます
◆捕捉1
当サイトからボキャビルを始めるメリットは、覚える英単語をカタカナ語に絞っているため、暗記に要する学習コストや苦手意識を低く抑えられるところにあります。
◆捕捉2
次にJACET8000やSVLに進む理由は、それぞれおよそ半数の単語を当サイトで覚えてしまっているので、その土台がない場合に比べて、圧倒的にサクサク進められ、かつ効率的に重要単語を身に付けられるからです(SVLを最後まで終わらせない理由は、その次元になると単語の重要度順が誤差と呼べる範囲となり、暗記能率がそれほど高いものではなくなるためです。もちろん12000まで覚えても何も問題ありません)。
◆捕捉3
最後に自身が興味ある分野、あるいは関与する分野での頻出語を重点的に覚える理由は、特定分野の単語をネイティブ全般の頻度順に覚えようとすると、暗記対象となる単語数が数万(ひょっとすると十数万)にも上り、まったく賢い方法とは言えないからです。それよりは直接その特定分野に頻出する単語を覚えてしまった方が、手間もかからず効率もよいものとなります。2.の段階で基本的な単語力はすでに身についているので、何か不都合が生じることもありません。
英単語カバー率の比較
このサイトではカタカナ語として6000の英単語を紹介しています。そのうちVoice of America(VOA)でSpecial Englishとして設定されている単語リストに含まれる単語は1201個です(カバー率79.5%)。JACET8000に含まれる単語は4665個です(カバー率58.3%)。究極の英単語12000に含まれる単語は5634個です(カバー率46.9%)。
なお、ビジネス用コミュニケーションツールとしてグロービッシュ(グローバルとイングリッシュをかけあわせた造語)を提唱したジャン=ポール・ネリエール氏は、基本単語として1500語のリストを作成しましたが、その時に彼が参考にしたものが、VOAのSpecial English Programにおける基本単語1500語(2014年2月現在では1510個)です。当サイトできっちりボキャビルすると、Special Englishのリストから覚えなければならない単語は、残り309個となるので、ビジネス用コミュニケーションツールとしてグロービッシュを身につけたい場合にはチャレンジしてみるとよいでしょう。
ちなみに、JACET8000は、British National Corpus(一億語)に、独自に作成した580万語のリストを追加し、そこから8000語を抽出したもので、この8000語によって英文に含まれる単語の97.3%(平均。固有名詞を除く)をカバーできるとされています。つまり、このサイトでボキャビルの基礎固めを終えた後、JACET8000の残る3335個を覚えたならば、あなたは英文に含まれる単語の97.3%を辞書なしで理解できるようになります(ただしJACET8000の書籍は入手しにくいので、同じ程度の水準にある究極の英単語の三巻までをチェックするといいと思います)。この数字の解釈には、JACET8000の概要が参考になります。そこには次の文が載せられています。「一般に、文章を構成する単語の95%程度がわかれば、その文章はおおむね理解可能だ」。
また、究極の英単語12000の第四巻には、このような言葉が添えられています。「最終巻のこの本では、TOEIC満点を超え、語彙マスターになる、超上級の3000語を学びます」。もしあなたが語彙マスターになりたいのであれば、当サイトでボキャビルを終えた後、SVL12000の残る6366個を覚えると良いでしょう(※究極の英単語12000とJACET8000では共通する単語も多いので、JACET8000を済ませた後、さらに6000語以上の単語を覚えなければならない、ということにはなりません。参考までにJACET8000にはSVLの単語が7501個含まれています)。
「英語をマスターするには数千も単語を覚えなければならないなんて……」と思われる方もあるかもしれませんが、実際にはカタカナ語だけでもかなり戦えるので、JACET8000やSVL12000への挑戦は、ほんとうに英語をかっちりやりたい人向けです。しかし、「英語を身に付けるには3万から4万の単語力が必要」といった言葉を聞いたことがある人の場合には、「たったの数千の暗記でいいの!?」と逆に驚かれるかもしれません。
母国語でも知らない言葉
新聞を一面から最終面まで熟読する人は少ないでしょう。ほとんどの人は興味があるところだけを拾い読みしているはずです。そして、読み飛ばしている紙面には、日本語ネイティブすら知らない単語が使われていることが珍しくありません。
例えばあなたは、ラグビーの用語をどれほど知っているでしょう? あるいは、医療保険改革の記事をスラスラと読むことができるでしょうか? もしくは、日銀短観の解説記事に使われている経済用語をすべて正確に説明できるでしょうか?
そう、新聞のように万人向けに作られた商品ですら、私たちはそこで使われている言葉に精通しているわけではないのです。これが資格試験のテキストや特定分野の用語集になれば、さらにお手上げになるはずです。いよいよ知らない単語のオンパレードに見舞われるだろうからです。
このように、ネイティブすら知らない単語が身の回りには数多くあるにもかかわらず、私たちは日本語ネイティブとして特に不便することなく生活できています。この辺はうまいこと脳がフィルタリングしてくれているのでしょう。
しかしこれが外国語となると、途端にパニックになります。どこからが特殊な用語で、どこからが普通の言葉なのか判断できず、知らない単語の数の多さに圧倒されがちです。興味の範囲を絞りきれていない場合はさらに深刻で、絶望的な気分に陥ることすらあるでしょう。「こんなにも知らない言葉だらけとは……」と。
けれど、ここはうまく開き直ることが必要です。まず興味の範囲を絞りこみ、そこでの用語に慣れてしまうことです。すると段々と特殊な用語やフレーズの見分けがつくようになります。余裕が出てきたら、徐々に別のジャンルへと手を伸ばしていけばよいでしょう。何も不安がることはありません。ネイティブだって、すべてのことがらに精通しているわけではないのです。ましてや外国語を学んでいる者にとっては、という話です。
ネイティブも学習する
語学学習に終わりはない、とはよく聞くフレーズですが、実はネイティブも母国語を学び続けています。日本語の場合でもそうです。
たとえば、年末に新語、流行語の類いがリスト化されますが、そのすべてを知っている人はそう多くないでしょう。私たちはそこで気になる言葉があれば、さっと目を通して記憶します。しかし母国語なので、学ぶという意識はあまりありません。たいていはスッと頭に入ります。けれども学習していることに変わりはないのです。
また、何も年末にだけ私たちは新しい言葉を覚えているわけではありません。普段から私たちは新しい言葉を覚え続けているのです。ほとんどはまったく無意識のうちに。たとえば、週刊誌の見出しに踊る奇妙なフレーズや、新しい技術や制度の記事に使われている特殊な用語を、知らず知らずのうちに学習しています。そうすることで私たちはネイティブとして生活できています。少しでもこの学習をサボってしまうと、ネイティブすらネイティブではなくなってしまいます。
なぜなら日々あたらしい用語が生まれてきているので、それらをうまく消化できていないと、母国語から取り残されてしまうからです。十年前の新聞と今の新聞をイメージしてみて、それからさらに十年後の新聞をイメージしてみてください。いきなり十年後にタイムスリップしたら、きっとあなたは記事をスラスラと読むことができなくなっているはずです。未知の出来事や風潮、技術、制度などが誕生し、それらに付随する言葉やニュアンスがうまく読み解けないだろうからです。ネットスラングの場合にはより顕著でしょう。
このようにネイティブさえ日々あたらしい言葉を学んでいるのですから、外国語を学ぶ場合にはより一層のトレーニングが欠かせない、と言えるでしょう。
データの罠
イギリスやブラジルといった国名はよく耳にしますが、アゼルバイジャンやトンガはそう多く耳にしません。もしトンガで何か世界的なニュースになるような出来事があれば、その時はトンガの国名を頻繁に聞くことになるでしょうが、そうでなければ今後もあまり耳にすることはないでしょう。
さて、頻度順に単語を並べると、上位の順位にはそれほど変動はないものの、(トンガの例のように)下位においては事情が違ってきます。観測条件によってランキングが大いに変動するからです。期間は過去五十年にすべきか、過去二百年にすべきか、口語か文語か、あるいはその両方か、両方の場合にはどのように重み付けするか、文語にはインターネットを含むか含まないか、口語にバラエティ番組やコマーシャルフィルムを入れるか、分野や地域をどのように絞るか、新語や死語、方言、スラング、ジャーゴンをどのように判定するか等々。
実はこのサイトの単語順も、下位についてはアバウトと見なされても仕方ない部分があります。しかしそれは避けようがないことだと思うので、あまり気にしていません。ほんの誤差とも言えそうなところで順位が大きく変わってくるからです(ホントに)。けれど上位3000語くらいまでは、わりかし変動幅が小さいように思います。これは究極の英単語やJACETの順番を見てもそう感じるので、きっとそういうものなんでしょう。
タイトルをデータの罠としましたが、何かの落とし穴というわけではないので、この話に特にオチはありません。