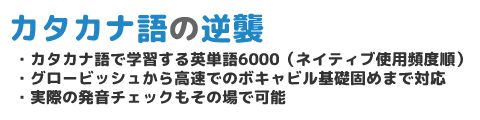ネイティブも学習する
語学学習に終わりはない、とはよく聞くフレーズですが、実はネイティブも母国語を学び続けています。日本語の場合でもそうです。
たとえば、年末に新語、流行語の類いがリスト化されますが、そのすべてを知っている人はそう多くないでしょう。私たちはそこで気になる言葉があれば、さっと目を通して記憶します。しかし母国語なので、学ぶという意識はあまりありません。たいていはスッと頭に入ります。けれども学習していることに変わりはないのです。
また、何も年末にだけ私たちは新しい言葉を覚えているわけではありません。普段から私たちは新しい言葉を覚え続けているのです。ほとんどはまったく無意識のうちに。たとえば、週刊誌の見出しに踊る奇妙なフレーズや、新しい技術や制度の記事に使われている特殊な用語を、知らず知らずのうちに学習しています。そうすることで私たちはネイティブとして生活できています。少しでもこの学習をサボってしまうと、ネイティブすらネイティブではなくなってしまいます。
なぜなら日々あたらしい用語が生まれてきているので、それらをうまく消化できていないと、母国語から取り残されてしまうからです。十年前の新聞と今の新聞をイメージしてみて、それからさらに十年後の新聞をイメージしてみてください。いきなり十年後にタイムスリップしたら、きっとあなたは記事をスラスラと読むことができなくなっているはずです。未知の出来事や風潮、技術、制度などが誕生し、それらに付随する言葉やニュアンスがうまく読み解けないだろうからです。ネットスラングの場合にはより顕著でしょう。
このようにネイティブさえ日々あたらしい言葉を学んでいるのですから、外国語を学ぶ場合にはより一層のトレーニングが欠かせない、と言えるでしょう。
データの罠
イギリスやブラジルといった国名はよく耳にしますが、アゼルバイジャンやトンガはそう多く耳にしません。もしトンガで何か世界的なニュースになるような出来事があれば、その時はトンガの国名を頻繁に聞くことになるでしょうが、そうでなければ今後もあまり耳にすることはないでしょう。
さて、頻度順に単語を並べると、上位の順位にはそれほど変動はないものの、(トンガの例のように)下位においては事情が違ってきます。観測条件によってランキングが大いに変動するからです。期間は過去五十年にすべきか、過去二百年にすべきか、口語か文語か、あるいはその両方か、両方の場合にはどのように重み付けするか、文語にはインターネットを含むか含まないか、口語にバラエティ番組やコマーシャルフィルムを入れるか、分野や地域をどのように絞るか、新語や死語、方言、スラング、ジャーゴンをどのように判定するか等々。
実はこのサイトの単語順も、下位についてはアバウトと見なされても仕方ない部分があります。しかしそれは避けようがないことだと思うので、あまり気にしていません。ほんの誤差とも言えそうなところで順位が大きく変わってくるからです(ホントに)。けれど上位3000語くらいまでは、わりかし変動幅が小さいように思います。これは究極の英単語やJACETの順番を見てもそう感じるので、きっとそういうものなんでしょう。
タイトルをデータの罠としましたが、何かの落とし穴というわけではないので、この話に特にオチはありません。
アスパラガスは専門用語?
「英単語を一万も覚えたら、ほとんどの英文を読めるようになるのでは?」と、一万という数字のインパクトに惑わされて、私たちは思ってしまいがちですが、それは半分ほど正しくて、半分ほど間違っています。正しさについては、JACET8000の数字「97.3%」に委ねるとして、間違っている点については、次のような単語がJACET8000やSVL12000に含まれていないことで明らかになると考えます。
- アスパラガス(Asparagus)
- トライアスロン(Triathlon)
- コラーゲン(Collagen)
アスパラガスもトライアスロンもコラーゲンも、一般的な日本人ならば普通に知っている言葉です。日常それほど頻繁に耳にするわけではないものの、専門用語のたぐいではありません。
さてここで「一万語の英単語って、その程度なんだ……」とガッカリする必要はないです。ボキャブラリーが一万もあれば基礎的なところはほぼ完璧なので、あとは分野を絞って単語を覚えたらいいだけだからです。料理に興味があるなら、早い段階でアスパラガスやそれに類した単語に出会うでしょうし、スポーツであればトライアスロンに、美容であればコラーゲンにやはり早い段階で出会うでしょう。
逆に分野を絞っていなければ、そのような単語に出会う時期はとても遅くなるでしょう(ネイティブ全般の使用頻度順に単語を覚えた場合、途中から非常に効率が悪くなるというのは、自分の興味関心とは無関係な分野の単語を、多く暗記する羽目になるからです。そして「英語を身に付けるには、少なくとも三万語は必要」といった言葉は、効率の悪いボキャビルを選択してしまった場合のものだと思います)。
英単語を何から何まで覚えようとすると大変ですが、一万位外のものについては自身に関係ありそうな場合にだけ覚えるようにすると、有益ですし効率的です。ここで挙げたアスパラガス、トライアスロン、コラーゲンの例は、単語を覚える時の目安にもなるかと思います。すなわち、トマトやポテトといった単語は一万語に入っていますが、アスパラガスは入っていません。同様に、テニスやフットボール、あるいはダイエットやエクササイズは一万位内に入っていますが、トライアスロン、コラーゲンはそこに含まれていません。
ボキャビルにおける「専門用語」ないし「特殊用語」が、ある程度イメージできてくるのではないでしょうか。実はこの見分けができる、できないで、未知の英単語との付き合い方がグッと楽になります。自分に無関係そうな分野の単語は、無理に覚えなくてもすませられるようになるからです(もちろん覚えるにこしたことはないのですが、単にツールとして英語を使いたい場合には、その辺の労力を省いても問題ないと考えます。それよりはリラックスした態度で英語と向き合うことの方がよほど重要でしょう)。
受験英語やTOEICについて
当サイトは、受験やTOEIC対策向けに作られていません。しかし実際に役立つ単語力を効率よく身につけられるので、間接的には役立つでしょう。
ちなみに世間での評判が芳しくない受験英語ですが、コーパスが一般化する前から存在していたにもかかわらず、重要な単語をうまくカバーしているので、英単語の使用頻度順といった観点からすると、素晴らしくよくできていると思います。大学受験レベルの英単語については、最難関校クラスであっても、(使える英語という視点からすると)基礎のところに位置するので、絶対に覚えて損はありません。
TOEICもまた様々な批判に晒されることが多いですが、試験自体についてはよく出来ていると思います。というかTOEICにはまったく罪はなくて、TOEIC至上主義や試験テクニック先行型の参考書などに問題があると考えます。なぜならそういったものは、「実際に使える英語をモノにできているか?」という本質とは無関係だからです。
ただTOEICの場合、若干「専門用語」が多い印象があります。「日常の会話で使うかなあ……?」といった単語の比重が高めなので。例えば、「上院議員」や「陪審」を交えた会話って、なかなかイメージできません(新聞の政治面や社会面を熟読する人が相手なら別ですが)。しかし力試しにTOEICを活用するのは、全然アリだと思います。